季刊誌 駒木野 No.199
新年を迎えて
駒木野病院 理事・副院長 田 亮介

新年あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。数々のご厚誼に対し改めまして御礼申し上げます。
2024年(令和6年)が始まりました。法人にとって大きな出来事としては診療報酬改定の年にあたり、さらには6年に一度の医療・介護・障害福祉サービスのトリプル改定となります。例年ですと3月初旬に告示、4月に施行という流れでしたが、今年は薬価改定以外の改定事項については6月1日に施行で了承されているようです。改定事項を確認しながら、日々の活動が単なる「いいこと」に終わらず、しっかり収益を得られるような工夫や調整が求められてくると思います。
4月からは「医師の働き方改革」もスタートします。時間管理は当然必要ですが、数字にみえづらい「働きやすさ」「働き甲斐」「充実感・満足感」「専門職としての成長実感」のようなものを職員がいかに感じることができるのかも大切だと考えます。2023年度の事業計画にも「安心で働きやすい職場環境の提供」を掲げていますが、医師以外の職種についても改めて健康管理・人材育成・働き甲斐について振り返り、推進していく機会にしていきたいと考えています。
昨年は障害者虐待に関連する報道や法整備が施行される中で、精神科医療に対して大変厳しい意見や評価を目にする機会が多くあり、どこかモヤモヤした気持ちを抱きながら過ごしてきました。一方で、コロナ禍で増えた自殺・うつ・不安に対して「メンタルヘルス」という言葉が注視され、「DPAT」の活動についても少しずつ浸透してきているように、我々の日々の精神科医療の取り組みに対する地域の期待は大きくなってきています。また、精神保健福祉法の改正により、精神障害者のみならず、「精神保健に課題を抱える者」も支援の対象となり、医療の枠組みにとらわれずに、我々が培ってきた精神科医療の知識とスキルをどのような形で地域に還元できるかということが求められてきています。今年は八王子版の「にも包括」も少しずつ動き始めていく予定で、何かしらの参画をしていくことになりそうです。法人各々の場での活動はもちろんのこと、地域を意識した活動・地域に出向く活動・地域を育てる活動が益々大事になってきています。
今年の干支は「甲辰」だそうです。東洋思想では古くより「言葉には天意が宿る」と考えられてきており、「甲辰」という言葉には「硬い殻を強く揺さぶって大きく成長させ、あるべき姿へと整っていく状態」との意があるそうです。「あるべき姿」とは何でしょうか?組織レベルでも個人レベルでも様々かもしれませんが、私が考えるのは「地域にも利用者にも職員にも、オープンで風通しのよい法人として現状に慢心せずに常にチャレンジしていくこと」、「法人に関わるあらゆる方々が安心と希望と自尊心をもって仕事や生活をしていくこと」と認識しています。しっかりと陰の部分にも光を当て、チャレンジし、法人の理念や将来の大望を叶えるための準備が整う年との意味もあるのではないかと思っています。この「あるべき姿」を目指して、しっかり考え抜いて、しっかり実行にうつしていく年にしていきましょう。
最後になりますが、本年が皆様にとって実り多き一年でありますように祈念して、年始のご挨拶とさせていただきます。
サービスステーション駒木野
Service Station Komagino
SSKの名称で親しまれ、そのフットワークで様々な活動に従事する、サービスステーション駒木野その成り立ちゃ、活動について改めてご紹介します。

SSKの成り立ち
サービスステーション駒木野( 以下SSK) は1997年1月に組織されました。当時の職員は看護師1名、PSWl名
の2名であったものの、SSK運営委員会も組織され、副院長・看護部長をはじめ複数の部署•他職種から委員が選出されました。
SSKがまず取り組んだことは、病棟から実施していた訪問看護をシステム化することです。病院として訪問看護を拡充し、外来サービスのクオリティを向上されることを使命としてSSKはスタートしました。さらに訪問看護を実施していく中で、「患者様の地域生活を直に感じた」事が足掛かりとなり、新しいデイケアのプログラムも開始されました。
当時の様子は駒木野病院30周年記念誌に詳しく書かれておりますので、ご興味のある方は是非ごー読ください。
SSKの今 と これから
SSKは病院や地域に無い事、形になっていない事を具現化することからスタートし、その活動を続けています。
時代により求められる役割、業務も異なり、それに合わせてSSKも変化してきました。
2020年度からは「SSK」「デイケア」「アルメック」「すこやか」の4部門が一つの部となり、リカバリー応援部として新たに組織されました。今までより幅広く他部門と連携し、ご利用者の回復につながる活動をひたむきに続けていきたいと考えています。
現在のSSKの活動は、患者様ご本人への支援、ご家族への支援、地域連携、精神保護福祉関連の情報提供など、多岐にわたります。その一部を以下にご紹介します。
文:萩原
患者様ご本人への支援
退院支援委員会
院内の委員会のひとつに位置づけられていて、定村先生を委員長に活動を行っています。
毎月第3火曜日15:00~委員会を開催し、年間約半分は各部署の持ち回りで事例検討会を開催しています。この事例検討会には地域事業所の方にも参加頂き、地域の視点でご意見をいただいております。また通常月の委員会は各病棟から退院支援の進捗状況の報告があり委員会全体で共有し、意見交換をしています。その中でSSKは委員会の事務局の役割も担っています。
院内や地域の方を講師に学習会も実施しており、障害福祉サービスや介護保険等、また委員会メンバーが今知りたいことをタイムリーに拾い上げて学習会のテーマとすることもあります。
退院支援委員会の日常但蛍動
- 長期入院患者様の退院支援のため、委員会コアメンバーで月1回退院支援コア会議を開催しています
- 地域関係者と院内閲係部署を繋ぎ連携・協働を図りながら利用者中心の退院支援を進めています
- 法人内の事業所とも連携し、退院支援を進めています
- 退院準備プログラムてくてく、地域定着支援グループふくふく、ピアサポーターの病院訪問等の運営及び調整を行っています
文:水野
てくてく
2014年より、退院支援委員会主催で退院準備プログラム「てくてく」を開始しました。
退院支援の一環として、グループワークを用いて本人ヘアプローチしています。目的は「退院した後も、地域で安心して生活できるように準備をする」こと。「プログラム参加=退院」ではなく、少しでも退院に近づけるための一つの材料で
す。
看護師・ソーシャルワーカー・作業療法士と多職種での運営と同時に、各セッションの宿題を通して病棟主治医・担当看護師•他にも多くのスタッフにも御協力いただいています。プログラムで扱う内容は病気の症状や服薬のことからはじまり、退院後の生活をイメージするための通所施設や居住施設の見学、困りごとを相談するための具体的な方法を学ぶSSTなど多岐に渡ります。
1クール14セッションを通して入院中から退院後まで役に立つさまざまなことを学ぶ中で、退院後の生活イメージが持てるようになること・退院へのモチベーションを上げること・積極的に相談できるようになることを目的とすると同時に、病棟スタッフ・退院支援員会(個別退院支援委員)との連携で、より個別支援へ繋ぎやすくします。
文:吉野
ご家族のサポート
ファミリープログラム
ファミリ_プログラムは、統合失調症で通院・入院されている患者様のご家族を対象とし
ています。
患者様ご本人にその方らしく生活してもらいたいという気持ちはもちろんのこと、私たちは「ご家族にも元気になってほしい」と考えています。そして、そのために何かできることはないかと考え、2012年にこのプログラムがはじまりました。
「統合失調症ってどんな病気なんだろう」「薬にはどんな効果があるのかな」「本人との関わり方はこのままでいいのかな」など、多くのご家族が抱える疑問について講義でお伝えすると同時に、身近でご本人を見守っているご家族だからこその悩みや不安について他の参加者と分かち合い、一緒に考えていくグループワークを行っています。コロナ禍で開催中止あるいは講義のみの開催となった期間もありましたが、2022年からは講義とグルーワークを組み合わせた本来の形式で再開しました。
プログラム終了後もご家族同士の繋がりやサポートグループヘの繋がりなど、継続した家族支援を生み支えています。
文:吉野
ピア活動・地域とのつながり・情報提供
いっぽの会
皆さまには「いっぽの会」の名前で親しまれておりますが、正式には八王子精神保健福祉ボランティアの会と言います。
精神保健福祉のボランティア講座を受講されたボランティアのみなさんが、月に2回第1、第3金曜日13:30に病院にいらっしゃり、傾聴活動をして下さります。傾聴活動というと大袈裟ですが、ボランティアメンバーさんも患者様(ゲストさん)もおしゃべりを楽しんでいます。
メンバーさんが時々お花をお持ち下さり、その場がパッと明るくなります。ゲストさんの笑顛も増えます。話題はその時々で色々です。食べ物のお話、お気に入りのスポーツ、旅行にいくならとこ? 時にはとうしたら退院できるの?退院するのがとても心配です、等入院中ならではの話題が飛び出します。ボランティアメンバーさんは穏やかにゲストさんのお話に耳を傾けてくださり、時間があっという間に過ぎていきます。
入院中の患者様が、職員以外の方と心穏やかに本音でお話が出来る貴重な時間を、ボランティアメンバーの方には提供いただいております。入院中の患者様はどなたでもご参加いただけます。
文:水野
オープンルーム
E棟1階のオープンルームは、入院、外来の患者様とそのご家族、職員が利用出来るお部屋で、精神保健福祉の様々な情報情報提供の場でもあります。

精神保健福祉等に関して学べるビデオ資料もあり、視聴が可能です。
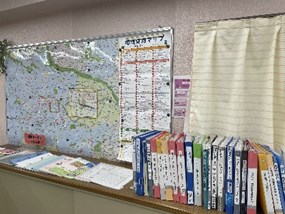
各地域の社会資料情報、疾病に関する書籍など様々な資料があり、どなたでも利用が可能です。

図暑の貸し出しもありますので、どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。お茶をご用意してお待ちしております。
文:萩原
学会活動報告
最近の学会活動のご報告です。
- 日本家族看護学会 第30回学術大会
「統合失調症の急性増悪で入院となった患者の親の生活の立て直しを支える看護師の関わり」
看護師:新名 匠 - 第54回日本看護学会学術大会
「精神科看護師が日勤帯で受ける言語的暴力の実態と職場内でのストレスコーピング」
看護師:大金 彩花・則村 良 - 第35回東京精神科病院協会学会
「救急病棟で関わりを持った若年層患者の精神科作業療法に対する意識とそこから広がる
ニーズに関して-入院生活と退院後の生活を送る患者個々へのインタビュー調査をもとに-」
作業療法士:森 結菜
うかふわプロジェクトイベント 駒木野アート展

今年のテーマは こまぎのmove です。世の中の様々なことがコロナ禍以前のように動き始め、私達の日常も少しづつ戻ってきている中で、感じたことや気持ちをアートで表現しました。1 ヶ月間の募集期間ではありましたが、多くの作品を応募いただき、展示にはたくさんの方にご来場いただきました。

11月の展示会に来られなかった方のため、1 月にはスクリーンでの上映会も行いました。作品応募いただいた皆様、スタッフの方々、ご覧いただいた皆様ありがとうございました。
うかふわプロジェクトイベント ウクレレ・ギター・フラを楽しむ会

昨年11 月14 日に、6 病棟を対象に、『ウクレレ・ギター・フラを楽しむ会』を開催しました。ウクレレ・シンガーソングライターのデイジー☆どぶゆきさん、アロハパフォーマーのアケミ アロヒナニさんをゲストに迎え、A4 ・B2 病棟担当医師の岡野先生にも歌・ウクレレでご参加いただき、大盛況で無事に開催することができました。コロナ禍にはかなわなかった生のパフォーマンス鑑賞を通じて、とてもよい時間を共有することができました。
編集後記
新年あけましておめでとうございます。年末に子供から「元旦ってなんでそう言うの?」と聞かれて答えに窮してしまうということがありました。早速調べてみると、「旦」という字はそもそも造語であり、太陽と水平線を意味しており「元旦」とは元日の朝を意味するということでした。子供と一緒に意味を読み返しながら、当たり前に使っている言葉の意味をあらためて知ることの楽しさをかみしめました。皆様はどのような「元旦」をお迎えになったでしょうか?願わくば朝だけでなく、豊かな実り多き日々の初日を迎えられていることを祈念いたしまして後記とさせていただきます。
ソーシャルワーク科 副部長 新井山 克徳